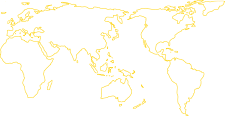2025年1月17日
はじめに
石破茂総理は1月9日から12日までマレーシアとインドネシアを訪問した。この外遊、1月20日の就任式の前に訪米してトランプに会うという目論見が潰えたためにはめ込まれた感が強い。だからというわけでもなかろうが、石破も旧態依然の東南アジア外交を繰り返した。日本がマレーシアやインドネシアに経済発展・民生改善(=給食支援を含む)・安全保障(=高速警備艇の供与など)等の支援を行うことによって中国に対抗する、というものである。だが、そんな東南アジア外交の効果は近年、著しく低下している。
第1に、もはや日本の国力は東南アジア諸国に対して絶対的に優位とは言えない。2000年時点のGDPを比較すると、日本経済はマレーシアの47倍、インドネシアの28倍だった。だが2024年になると、日本のGDPはマレーシアの10倍弱、インドネシアの3倍弱である。まだ日本の方が大きいが、圧倒的な差とは言えず、今後差は益々縮まる。それどころか、インドネシアのGDPは2030年代後半か2040年代には日本を抜くと予想されている。「大国の日本が支援・指導してやる」という〈上から目線〉のアプローチの効果は当然下がる。
第2に、東南アジアへのアプローチを強めているのは中国も同様である。その中国のGDPは今や日本の4倍以上。貿易関係でも、マレーシアの場合、日本からの輸入(2022年)は全体の6.4%、中国+香港からは22.7%。日本への輸出は全体の6.4%、中国・香港向けは19.8%だ。インドネシアの場合、輸入は日本からが全体の7.2%、中国+香港からは29.8%。輸出先は日本が全体の8.5%、中国・香港は23.6%となっている。[1]
米中対立の時代にあっても、東南アジアの大多数の国は米中のどちらかを選ぼうとはしていない。[2] むしろ日米と中国を競わせて双方からより多くの支援を引き出そうとしているのが現実である。
米中対立やトランプ再登場、そして日本経済の地盤沈下という現実を目の当たりにして、日本の東南アジア外交も発想を根本的に変えるべき時が来ている。AVP本号では、日本外交を覚醒させるための試案として「ASEAN加盟」論を提起する。
ASEANと日本
東南アジア諸国連合(ASEAN)はバンコク宣言(1967年)に署名したタイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポールが設立した地域機構である。当時はベトナム戦争の最中にあり、反共の砦として米国も後押しした。その後、ブルネイ(1984年)、ベトナム(1995年)、ラオスとミャンマー(1997年)、カンボジア(1999年)が加盟し、現在は10ヶ国体制だ。(東ティモールは2022年にオブザーバーとなり、正式加盟も間近とみられる。)
加盟国の政治体制は多様で、様々な水準の民主制、権威主義体制、王制、軍制が混在する。[3] 2023年の域内総人口は約6.8億人でEUの約4.4億人を上回る。域内の名目GDPは3兆8620億ドルで日本の約9割、EUの約2割。今後、日本を抜き、EUを追い上げることは確実だ。

(外務省ホームページより。)
EUと異なり、ASEANは国家主権を超越した共同体への志向性がとても弱い。組織の非制度化、〈全会一致〉の意思決定、内政不干渉などを重視した「アセアン・ウェイ」による運営は、時に「似非共同体」と揶揄される。その一方で、加盟国間で戦争が起きる心配をしなくてよい「不戦共同体」が事実上構築されたことの意義は高く評価されている。近年、ASEANは米中対立と距離を置くために「ASEAN中心性」(=東南アジアでの制度枠組みはASEANが中心になる、という概念)を強調しており、日米や中国もそれを無視できなくなっている。
現在、日本とASEANの間には、ASEAN+3(日中韓)、東アジア首脳会議、ASEAN地域フォーラム(ARF)アジア欧州会合(ASEM)や日・ASEANフォーラムなど多岐にわたる枠組みが存在する。ただし、日本はどこまで行っても〈数ある部外者の1人〉だ。このまま、冒頭に述べたような〈上から目線〉のアプローチを続けても、日本のASEAN外交は先細りするばかりであろう。活路を開くためには、日本はASEAN諸国に上位者として接することを止め、「日本も仲間になりたい」とASEANに飛び込んでいくしかあるまい。
豪州のASEAN加盟論
日本のASEAN加盟は荒唐無稽な話だろうか? そうとも言えない。現にASEAN加盟を戦略論として真剣に検討している先進国・民主主義国がある。オーストラリアだ。[4]
2012年、ポール・キーティング元首相(在任1991年12月~96年3月)は「長期的に見て我々はASEANのメンバーとなり、既に共有している貿易・商業・政治的な利益を制度的なものにすべきだ」と述べた。キーティングにとってASEAN加盟の目的は、豪州の国力と国際的地位の相対的な低下を補うこと、そして米国になびき過ぎた豪州の外交戦略をより自立的な方向に変えることだった。[5]
2021年にはケビン・ラッド元首相(在任2007年12月~10年6月、2013年6月~9月)も「豪州はASEAN加盟をめざすべきだ。豪州の加盟はASEANの経済力を3分の1以上引き上げるだろう。豪州と今後益々大国化するインドネシアが共に重要な地域機構のメンバーとなれば、両国関係の安定化にも役立つ」と主張した。
とは言え、2007年に採択されたASEAN憲章によれば、ASEANへ新規加盟できるのは東南アジアに位置する国に限られる。憲章を改訂しない限り、豪州や日本がASEANに加盟することは不可能だ。しかし、豪州のASEAN加盟論者はそんなことで諦めたりしない。
豪政府によって設立されたオーストラリア戦略政策研究所(ASPI)のグラム・ドーベルは2018年に「ASEAN共同体パートナーとしての豪州」という報告書をまとめ、ASEAN側の関係者とも協議したうえで豪州が実質的にASEAN加盟を果たすための方策を発表した。ドーベルの提案は、加盟国とは異なる「ASEAN共同体パートナー」という新しいカテゴリーを作ってもらい、豪州(及びニュージーランド)がその地位に就くというものである。もちろん、ASEAN共同体パートナーにはオブザーバーよりも強い権限が与えられる。
豪州がASEAN共同体パートナーになるためには、ASEANの全加盟国から承認されなければならない。ドーベルによれば、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領(当時)は豪州のASEAN加盟に前向きだった。シンガポールも常に賛成の意向を示しているらしい。態度が最も見通せないのは中国との関係が深いカンボジアとラオスだ。しかし、両国ともASEAN絡みの案件では必ずしも中国の言いなりにならないため、結果はやってみないとわからないと言う。
いずれにせよ、現時点ではまだ、ASEANへの実質加盟論が豪州政府の公式な政策になったという話は聞かない。しかし、豪州でASEAN加盟が現実的可能性を持った政策論として議論されていることは厳然たる事実だ。
ASEAN加盟の損得
正直なところ、日本がASEANに加盟することによって物凄く大きな安全保障上、経済上の直接的メリットがあるとは言い難い。例えば、ASEANに加盟しても、ASEAN諸国が日本防衛のために戦ってくれるわけではない。だが逆に、東南アジアで万一紛争が起きた時に日本が軍事的に関与する義務も生じない。
貿易・投資面では、2015年末に発足したASEAN経済共同体(AEC)によって物品・サービス、熟練労働者、資本の移動等の面で自由化が進めば、ASEAN加盟で得られる恩恵は小さくない。特に、人口減少が続く日本にとって、(移民という形をとるかどうかは別にしても)良質な人材をASEAN地域から確保できたらありがたい。ただし、AECはゆっくりとしか進まない可能性が高いため、あまり高望みすべきではないだろう。
全会一致で〈ゆっくり、漸進的に〉しか物事が進まないことはASEANの大きな限界である。裏を返せば、だからこそASEAN加盟の政治的コストは比較的低い。嫌ならノーと言えば、意に沿わないことは拒否できるからだ。
ASEAN加盟と自立外交
一方で、ASEAN加盟は日本外交に縦深性をもたらし、積年の課題である自立性の回復を後押しすると期待できる。この外交的なメリットは極めて大きい。
極論すれば、戦後の日本外交は日米同盟一辺倒でやってきた。日本人としての自尊心の問題を措いたとしても、それで良いのは「米国の判断が正しい」ことかつ「米国に従うコストが理不尽でない」ことという条件が満たされる時である。しかし、近年の米国は国際的にも国内的にも余裕を失い、おかしな決定が目に余る。気候変動問題への取り組みは度々逆行し、通商政策も自国中心の保護主義が幅を利かせるようになった。イスラエルが自衛とは呼べない非人道的な軍事行動を1年以上続けても米国政府はそれを黙認・支援してきた。昔は「日米安保があるから防衛費が少なくて済む」と言われたものだが、今は「守ってほしかったら防衛費を増やせ、米国から武器を買え、在日米軍駐留経費も実際にかかる以上に払え」と脅されている。挙句の果てに、日本製鉄のUSスチール買収は「同盟国であっても安全保障を損なう」と難癖を付けられ、中止命令を受けた。[6] 中国も問題ではあろうが、今や米国も別の意味で問題となった。間もなくトランプ政権の2期目が始まれば、我々はこれまで以上に「理不尽な米国」、「高くつく日米同盟」に直面するだろう。日米同盟一辺倒では益々どうにもならない。
それでも、日米同盟以外の選択肢を持たなければ、米国がどんなに間違えても、どんなに理不尽な要求をしてきても、日本は「米国に従うしかない」というメンタリティから抜け出すことができない。米国に注文をつけるにせよ、米国の要求を値切ったり拒否したりするにせよ、「我儘な米国」と付き合うために日本は〈ネットワーク力〉の構築に心血を注ぐことが不可欠だ。今、日本には国際社会で当てにできる仲間がいない。遅ればせながらでも仲間を作り、米国や中国とバイ(1対1)ではなく、マルチ(多対1)で対峙するのである。
そうした仲間候補の中で有力なのがASEANだ。ASEANは日本に近接し、経済的つながりも深い。そして、「米中対立に巻き込まれたくない」「米中対立を少しでも制御したい」と考えている点も、日本が本来持つべき戦略的目標と合致する。
そのうえで言えば、日本がASEANに(実質)加盟したいと希望しても、それが簡単に認められることはない。一昔前なら、日本という経済大国をメンバーにすることは「鯨を池に入れる」ようなものだ、という警戒感があった。だが今や、インドネシアのGDPは十数年後に日本を抜くと言われているし、シンガポールの1人当たりGDPは既に日本の2倍以上だ。「日本=鯨」論は絶対的な障害とはなるまい。
しかし、ASEAN側から見れば、〈米国の代理人としての日本〉をメンバーに加えれば、米中対立に巻き込まれて「ASEAN中心性」が崩壊しかねない。日本が米国にモノを言い、米中対立を制御するために〈ASEANと共に汗をかく〉姿勢を示してはじめて、ASEAN側は日本のASEAN加盟を真剣に検討するだろう。そこまで行けば、仮にASEAN加盟が実現しなくても、日本とASEANの関係は今よりも遥かに深みを持つはずだ。
おわりに
最後に付け加えると、ASEAN加盟論は停滞している東アジア共同体構想を活性化する起爆剤となる可能性を孕んでいる。実際、日本がASEAN加盟論というカードを持って独自の動きを見せれば、中国や韓国からも「バスに乗り遅れるな」という動きが出てくるかもしれない。
従来、東アジア共同体と言えば、日中韓を中核にするイメージが強かった。それは我々にとって自然な発想ではあるが、東南アジア諸国から見ると、日中韓が主役で東南アジアは付属品、という受け止めもあった。何よりも、日中韓にこだわってスタートラインにすら立てない状態を続けるより、〈緩い〉地域共同体ではあっても既に60年近い歴史を持つ、ASEANという実在の仕組みを活用するというアイデアには十分な魅力がある。「東アジア共同体なんて夢物語だ」と斜に構える前に、色々なやり方を試行錯誤したらよい。
[1] Malaysia trade balance, exports, imports by country 2022 | WITS Data
Indonesia trade balance, exports, imports by country and region 2022 | WITS Data
[2] 2024年4月に行われた調査では、米国と中国の選択を迫られた場合、中国を選ぶという答(50.5%)が米国を選ぶという答(49.5%)を初めて上回った。東南アジア “米より中国を選択”が初めて上回る 調査結果 | NHK | ASEAN 日本のメディアはその理由を「一帯一路など中国による貿易・投資の拡大」と解説している。だが最大の理由は、イスラエルのガザ攻撃を止めようとしない米国政府の姿勢がムスリム人口の多い東南アジアの一般国民を幻滅させたことである。
[3] 1967年当時の原加盟国も、現在の基準から見て民主主義国家と言える国はなかった。
[4] 本節の記述は下記を参考にした。Time for Australia to become a full ASEAN partner | The Strategist
[5] 20121114keithmurdochoration.pdf
[6] 経済合理性から見た正論としては、日本製鉄のUSスチール買収は認められて然るべきである。その点では、米国は確かにひどい。だが正直なところ、経営論的な視点からは、米国のカントリーリスクを過小評価した日本製鉄に同情する気持ちになれない。日本製鉄がUSスチールを買収すると発表したのは2023年12月。翌2024年は大統領選の年であり、誰もが大接戦を予想していた。近年の米国政治や通商政策の動向を多少なりとも観察していれば、買収に政治的な横やりが入るリスクは当然予想されるべきものであった。